養生按摩の訓 †
左の足の小指の端より、本節京骨の上を訣わかち、
踵を摩して
跗上(足の甲)大指の方へかけ然骨(舟状骨)の上を摩で、
足心湧泉にかけて解き、
外踝絶骨より三陰交へすじかいに摩で、底に滞りあらば骨ならば砕き、筋の変をばさすり摩で、
脛骨の中をすじかいに摩で、
三里の上邪骨を砕き、
膝蓋を砕き、
股へ上り陰市よりすじかいに摩で、
真中の胃経をくつろげ、
風市より胆経の環跳摩で、
横骨(恥骨弓上際)の末より腰骨腹にまわり、肉を分かち結ぼれを解き、
亀の尾(尾骨)の先より腰眼の穴あばらにかけて摩で、肌を解き、
二十一の脊骨より二行通り、肋先を解かし、
前にかかって摩で、
痞根、日月の位より結ぼれを解きて、
十三あたりの椎の骨より二行通りの肉を解き、
前は乳中、乳根の位を按摩し、
十一の椎より(是より上へ摩す)二行通りにかけ督脈を大椎の端まで摩で、骨をゆるやかにし、
九十の兪(肝兪、胆兪)より大腸経の肩髃を摩で、
肩骨の先を砕き(肩骨長くは念を入りたく)、
腋下にまわし、
肩骨のはずれ七の兪よりすじかいに二行通りの肉を砕き、
参考:「和漢三才圖會」巻第十二支体部
胸の上の横骨を巨骨という。その上の陥中(くぼみ)が欠盆である。
肩髃にかかり欠盆をくつろげ、肩骨を摩でて、
髆上(俗に二の腕と云)を摩し、
五の椎より膏肓の所にかかり、肩骨を摩で
肩井欠盆を和げ
前の方欠盆骨より脇の下に摩で肉を訣つ
夫れより骨先を砕き、肩骨欠盆、臑骨(俗に二の腕と云)の先を砕き、筋を分け斜に肺経の結れをとき、
臂骨の先より肉を分け太淵に至り(俗に脉所と云)斜に摩で解結し、
腕後より(俗に手首と云)大指にかけて摩て爪際をまわし摩で
合谷より大指の中、赤白肉のさかいを指先にて摩で解し、
腕後より五つの指、すちかひに摩して大指のごとく節々の骨を平げ滞りを去り、
爪のきわに氣をつけ(大指の如くす)指先をまわし摩ること数返。
参考:「和漢三才圖會」巻第十二支体部
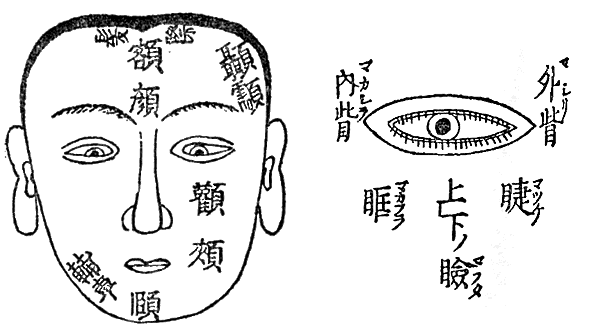
脳後(※百会の後下)骨を解き、完骨を(耳後の骨)左右共に揩砕き
曲鬢の(胆経)結肉を訣ち
顴骨(耳前の骨)動かし
眉骨を摩解し
上胞(※うわまぶた)鋭眥(※まなじり、目の外角)骨先を解し内眥(※目の内角)骨を解き
百会に摩であげ、眉の上を横になで、鼻をうごかし(掌の裏にて)人中を動かし摩で
内眥よりなで、耳の上曲鬢より脳後へかけ摩す。
頬車骨より上へ摩で百会のむすぼれをとき脳後の枕骨(※後頭隆起)を動かし摩でる(櫛を以て専らけづるもをし)、
髪際の邪骨を砕き、
左右の腮(※あご)の下へ骨をかけて摩でる。
髪際より斜に二三返も摩で、大椎の骨先を砕く。
欠盆を和げ欠盆骨を越す。
二三の椎より肩の上天髎巨骨へ摩で肩骨を摩す。
肩先より膏肓骨を越し二行通りの肉を動かし脊骨を越して摩でる。
腋下より手を当て七の椎脊骨を越す。
肋の下を日月の位より二行三行通りを越し十一二の椎を越す。
章門より手をあて膏肉を解し、二行通りの肉を解き、督脈を訣け摩でる。
腰骨の中の高き処より十七八の椎骨を越す。(右の股まて也)
腰骨環跳の位より手を付け、亀の尾に越し、横骨の末を摩つ。
風市の処を斜に髀関(俗に太股と云)より二十一の椎に當て摩す。
膝の上へ伏兎より風市にかけ摩す。(風市より下はのぼり摩す)
膝蓋のきわより斜に上へ摩す。
脛骨(※原文脛は肉月に行)を斜に陽明経を摩て越す。
大指の先き爪をわまし隠白大敦を摩。
足の裏を中指の先きより小指の方へ横に摩す。
大指の骨より湧泉にかけ、爪して肉を割摩る。
内踝より上へ、環跳まで斜に摩て上る。
右の如く行へは、万病不生。
延年にして不老。
貴も賤も、老少男女を不撰、常々油断なく慎て勤べし。
初心の人かならず是を習しめ、能々熟して後、痞滞を療る事をさとり知らしむへし。
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)